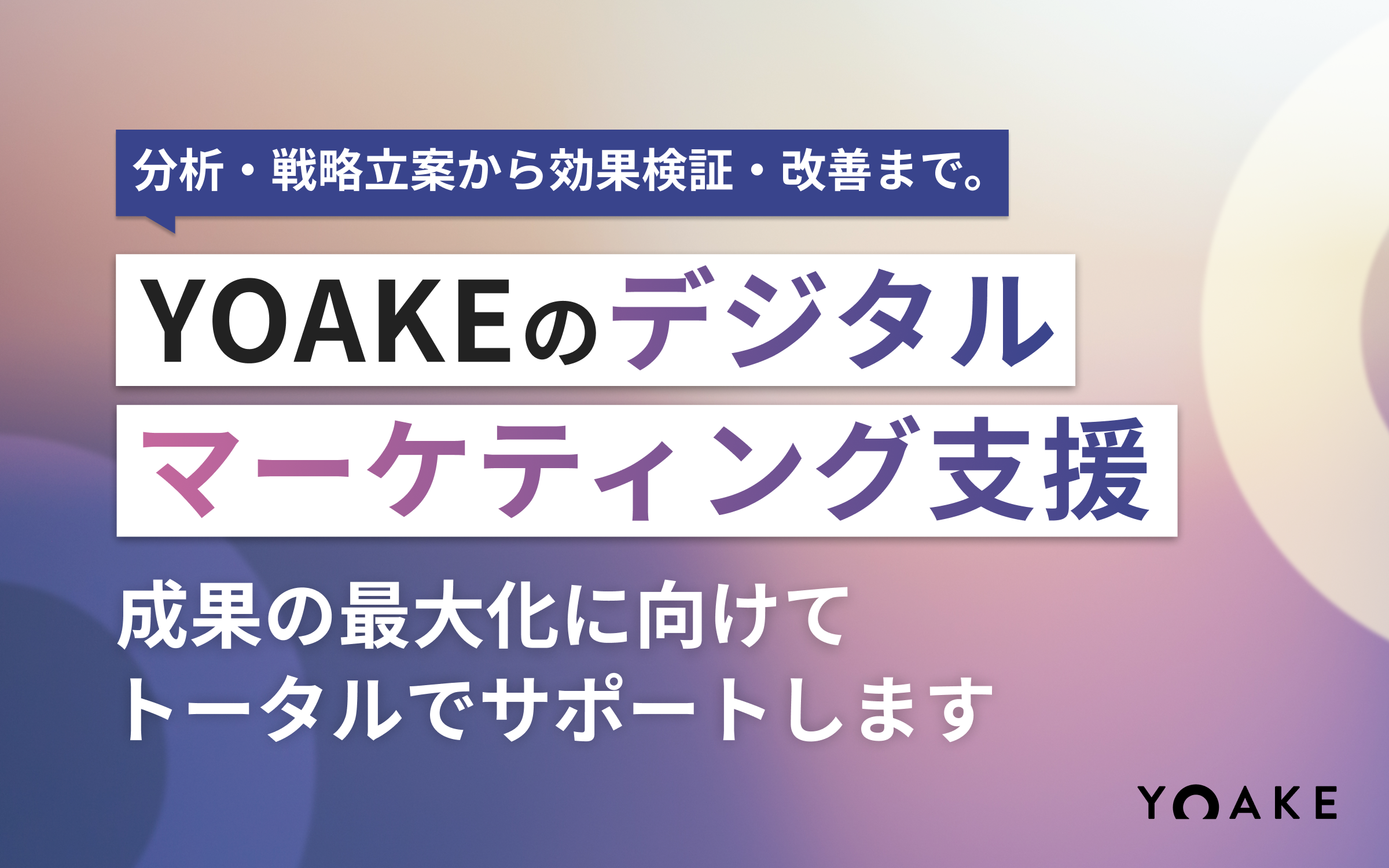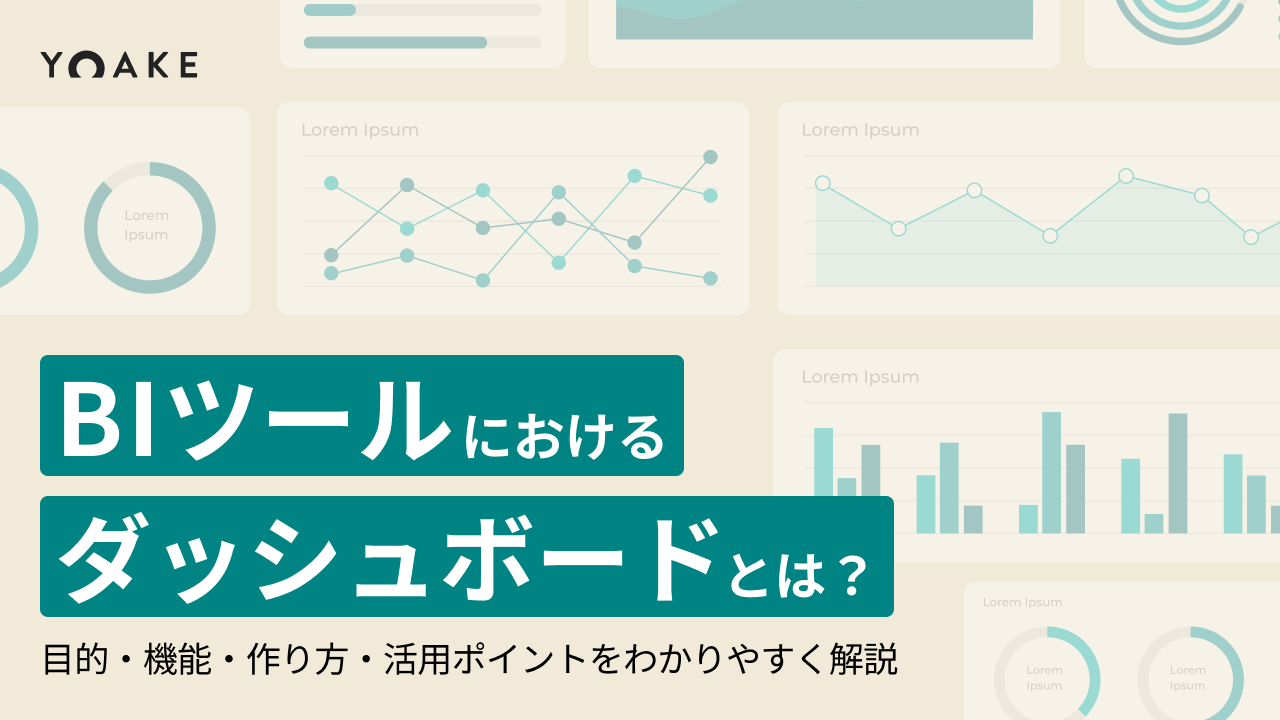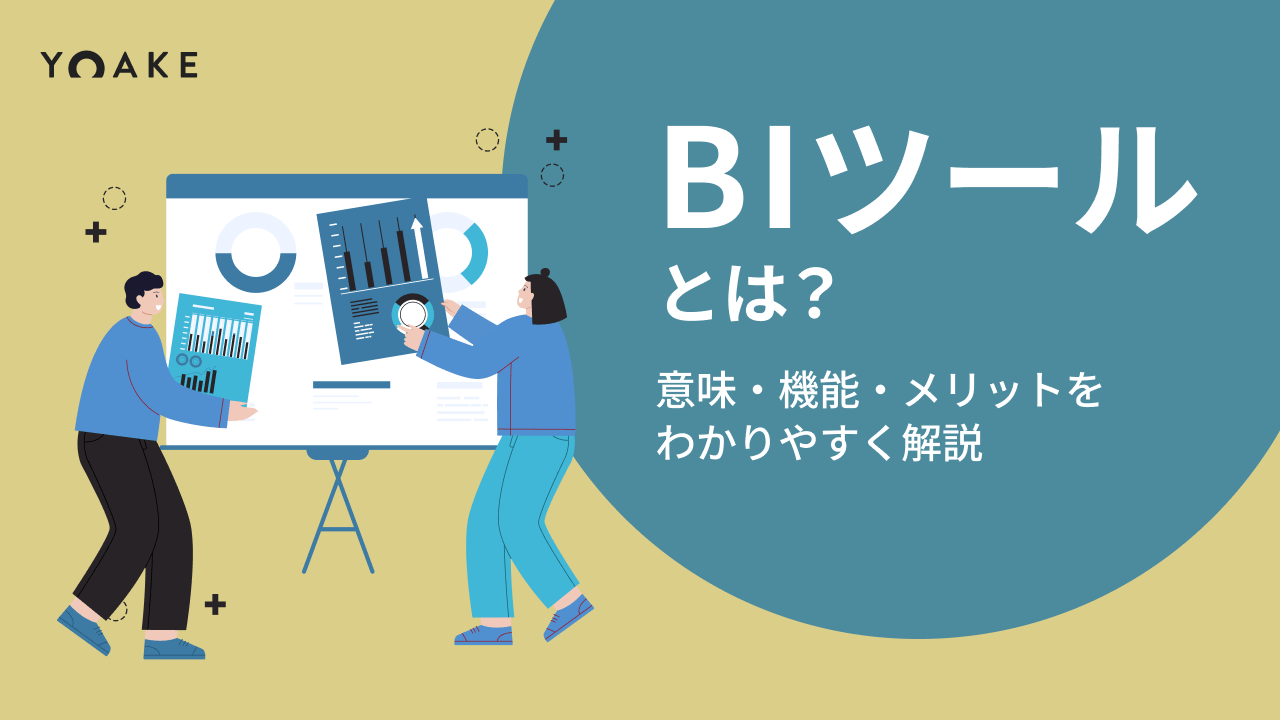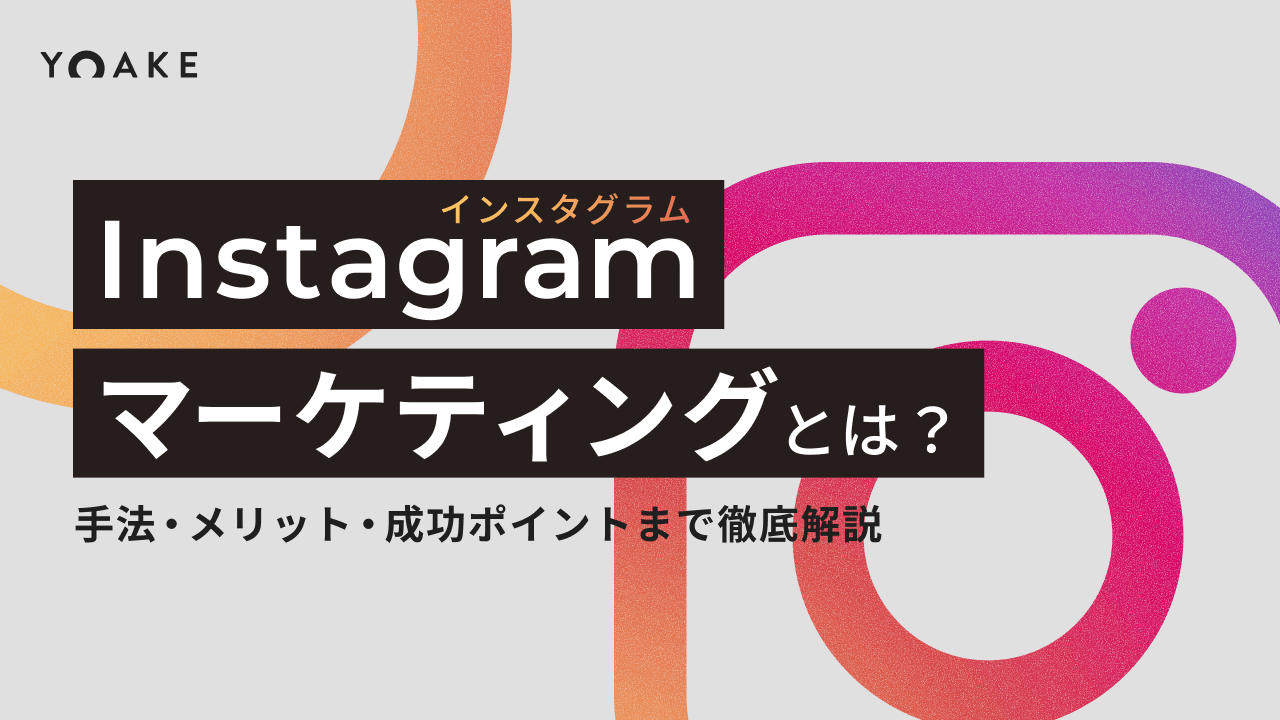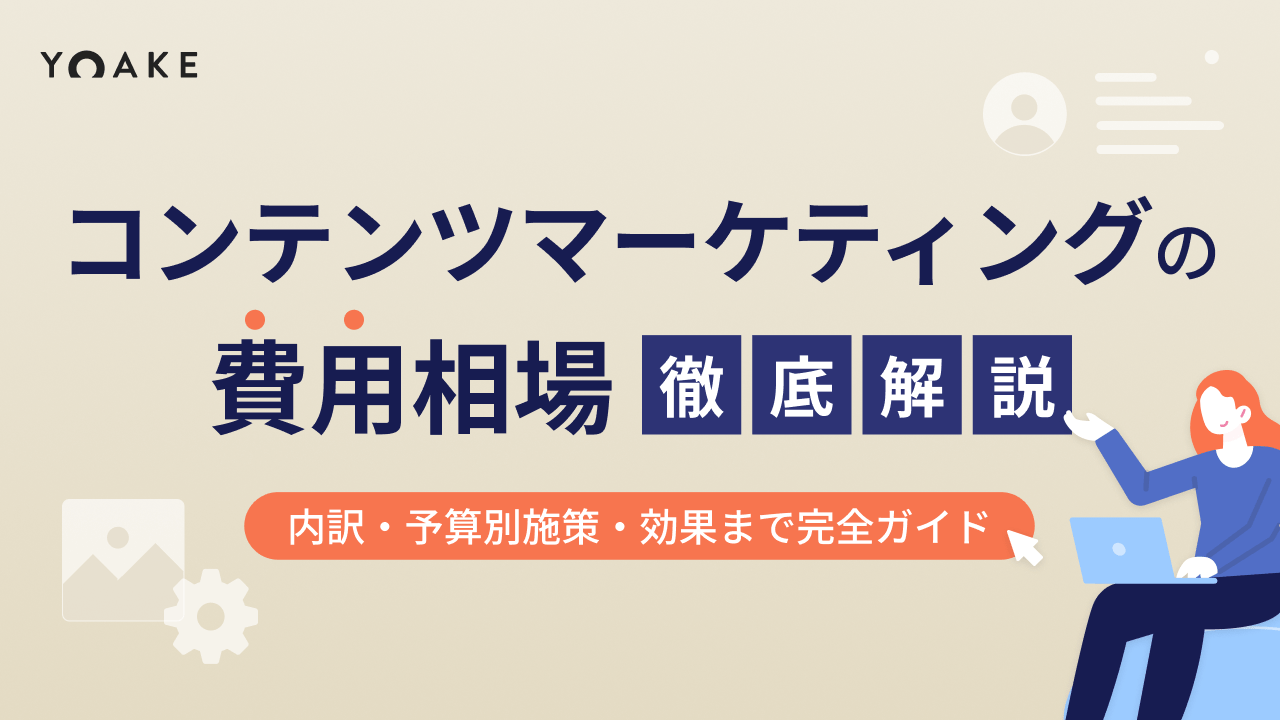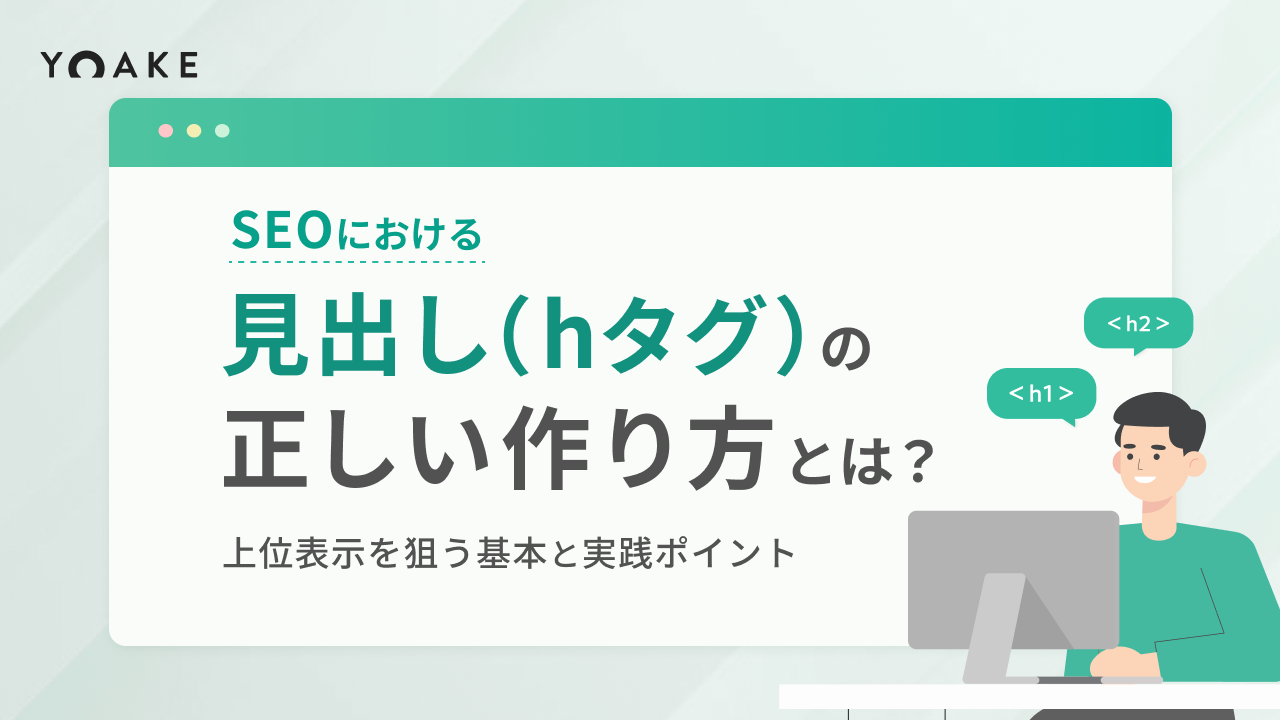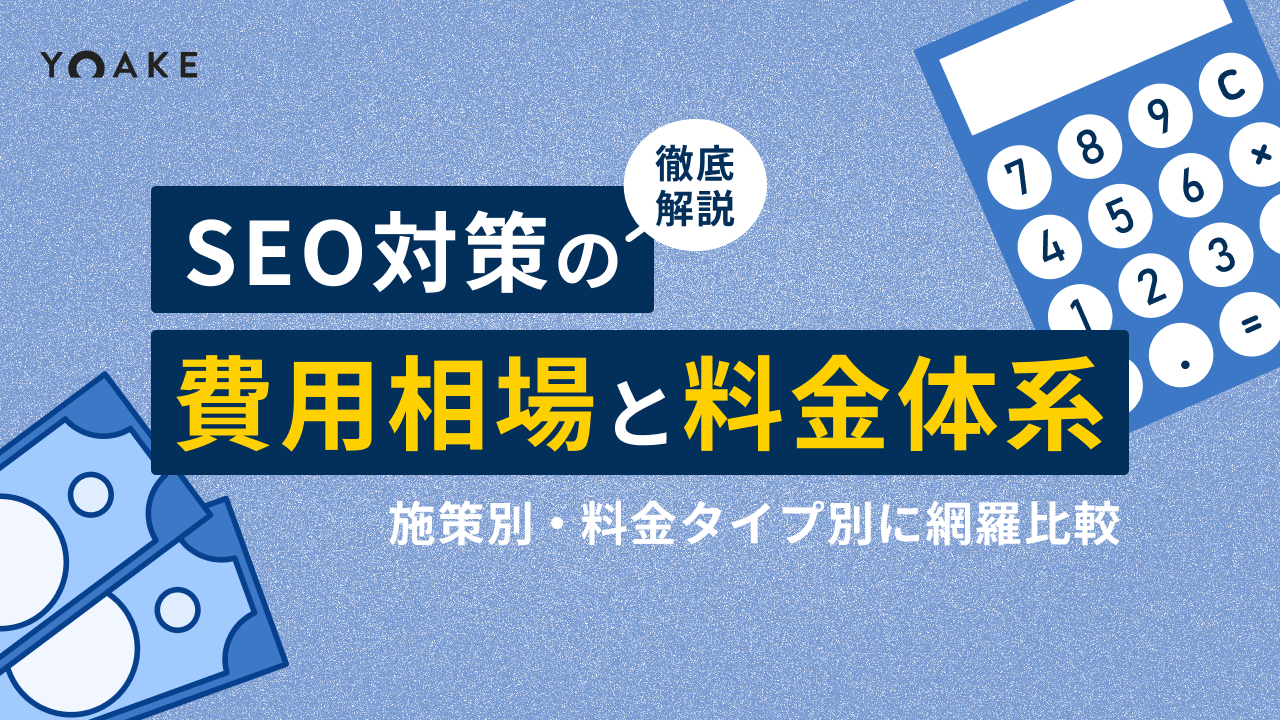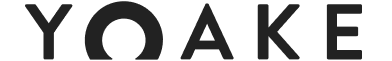E-E-A-Tの基本概念
E-E-A-Tは、Googleがコンテンツの品質を評価する際に使用する4つの要素の頭文字を取ったもので、Experience(経験)、Expertise(専門性)、Authoritativeness(権威性)、Trustworthiness(信頼性)の4つの要素から構成されています。これらの指標は、それぞれ単独で評価されるのではなく、相互に関連しながら総合的にコンテンツの品質が判断されます。
また、検索エンジン最適化(SEO)スターターガイドには、「E-E-A-Tをランキング要因と考えることはない」と明示されていますが、厳密には少し違います。直接的にE-E-A-Tをスコア化しランキング要因にする、ということはしていないというだけで、実際にはGoogleはE-E-A-Tを「検索ランキングシステムのパフォーマンスを検索評価者が評価するために使用するもの」としています。少しややこしいですが、ランキングを決定するシステムが適切かどうか、E-E-A-Tという指標を使って評価しており、E-E-A-Tの基準に満たない場合は調整する、ということをしていると考えて良いでしょう。そのため、E-E-A-Tは順位に関わる指標であり、SEOとして順位向上を見込むためには押さえておかなければならない要素であるといえます。
E-E-A-Tの4つの要素
先述したとおり、E-E-A-Tは、Experience(経験)、Expertise(専門性)、Authoritativeness(権威性)、Trustworthiness(信頼性)の4つの要素から構成される評価基準です。それぞれの要素が具体的にどのようなものなのか、解説していきます。
Experience(経験)
Experience(経験)は、実際の体験に基づいたコンテンツの価値を評価する要素です。たとえば、商品レビューでは実際にその商品を使用した経験に基づいた詳細な感想が求められるほか、旅行記では実際に訪れた場所での具体的な体験談などが挙げられます。
経験が重要視されるようになった理由は、よりユーザーが求める情報に寄り添うためといって良いでしょう。商品レビューではメーカーからの解説ではなく、第三者の目線で実際に使用した情報の方がユーザーが求める情報に近くなりますし、旅行コンテンツでも同様のことがいえます。価値あるコンテンツを作るには、こういった手触り感のある情報を掲載することが、SEO的な優位性を担保するといえます。
Expertise(専門性)
Expertise(専門性)は、コンテンツの執筆者やWebサイトそのものが持つ専門性を表しています。たとえば、医療情報を提供する場合は医師の資格や経験、金融情報を提供する場合は金融の専門知識や実務経験など、執筆している人やWebサイトの運営元が、それらの専門知識をもっていることが分かる状態にすることが重要です。
執筆者の表示だけでなく、サイト自体の構成も重要です。たとえば、あるジャンルについて専門性の高い人物が深く解説しているページがあったとしても、そのページ以外にそのジャンルについて深く解説したり、関連したコンテンツを用意できていない場合は、サイト全体の専門性は高くならず、順位が上がらない場合があります。E-E-A-Tに対応するためには、ページ単位で考えるのではなく、サイト単位で考えることも大切です。
Authoritativeness(権威性)
Authoritativeness(権威性)は、コンテンツやその提供者が特定の分野においてどれだけ信頼されているかを評価する要素です。業界での実績が他のメディアで言及されていたり、SNSやWebサイトで紹介されていたり、といったことが含まれます。この「他のメディアで紹介されているかどうか」という概念を、サイテーションと呼びます。コンテンツのサイテーションの高さを示すことで、権威性を高めることが可能となります。
重要なのはWeb上で言及されていることで、たとえばその道の権威である人が執筆を担当したとしても、これまでWeb上で言及されたことのない人物である場合、権威性を示すことは難しくなります(ただし、オフラインの言及のみだからといって効果が全くないわけではありません)。Googleはあくまでインターネット上の情報の方がアクセスしやすいため、Web上での権威性という点で評価を考える必要があります。
Trustworthiness(信頼性)
Trustworthiness(信頼性)は、コンテンツやその提供者が全体的にどれだけ信頼できるかを評価する要素です。情報の正確性、透明性、プライバシーへの配慮などが総合的に判断されます。例えば、運営元の明示やプライバシーポリシーの提示、通信の暗号化が適切に行われているか、といった点が挙げられます。
また、信頼性は、他の3つの要素(経験、専門性、権威性)を満たした結果、生まれる概念ともされています。信頼できるサイトで、信頼できる執筆者が独自の視点を交えて提供し、内容の正確さやサイトとしての安全性も考慮されたものが、真に信頼できるコンテンツといえるでしょう。
GoogleがE-E-A-Tを重視する理由
GoogleがE-E-A-Tを重視する背景には、ユーザーに質の高い情報を提供したいというGoogleの意図があります。インターネット上には膨大な量の情報が存在し、その中には誤った情報や信頼性の低いコンテンツも少なくなく、社会問題に発展した例もあるのが現状です。そのためGoogleは、ユーザーが信頼できる情報にアクセスできるようにするため、E-E-A-Tという指標を導入しました。
また同時に、Googleの検索アルゴリズムは、ユーザーの検索意図を理解し、最も適切な情報を提供することも目指しています。E-E-A-Tの評価基準はこの目的を達成するためにも役立てられており、たとえば、前述したように医療に関する検索クエリに対しては、専門家が執筆した信頼性の高い情報を優先的に表示することで、ユーザーに正確な情報を提供するように努めています。
E-A-TとE-E-A-Tの関係性
E-E-A-Tは、以前より使用されていたE-A-T(Expertise、Authoritativeness、Trustworthiness)から、2022年にExperience(経験)が加わってできた評価基準です。この背景には、Googleのコンテンツ評価に対する考え方の変化があります。従来のE-A-Tでは、専門性、権威性、信頼性の3つの要素が重視されていましたが、近年になって実際の経験に基づいたコンテンツの重要性が認識されるようになり、Experience(経験)が新たに追加されました。Experience(経験)が新たに追加されたことで、コンテンツ制作において単なる知識の羅列ではなく、実際の経験に基づいた価値のある情報を提供することが重要となったといえます。
E-E-A-Tは、Googleがユーザーに提供する情報の質を向上させるために重要と考えている要素であり、今後もE-E-A-Tは、コンテンツの品質を判断する上で重要な指標となっていくと思われます。
E-E-A-TとYMYLの関係性
YMYL(Your Money or Your Life)とは、ユーザーの「お金」や「人生」に重大な影響を与える可能性のあるテーマを指し、たとえば医療、法律、金融などが該当します。これらの分野では、不正確な情報や信頼性に欠けるコンテンツが深刻な結果を引き起こす可能性があるため、Googleは特に厳格な評価基準を適用しています。
その評価基準の中核をなすのが、E-E-A-Tです。YMYLに関するコンテンツが検索上位に表示されるためには、筆者がその分野において十分な経験や専門知識を有していること、情報発信者として信頼されていること、そしてコンテンツが正確で安全性の高いものであることが特に求められます。
逆に言えば、E-E-A-Tを示せていない場合、どんなに丁寧なコンテンツを作ったとしても、検索結果に表示させることは難しいといえるでしょう。執筆者や運営者がYMYLに関わるジャンルに明るい場合でも、サイト上にどのような要素を配置してGoogleにE-E-A-Tを示すかはSEO的な知見が必要です。
E-E-A-Tを高める12の具体的な施策
ここでは、E-E-A-Tを担保して検索順位を高める具体的な施策について解説します。
体験談の掲載
体験談のように、実体験に基づいた失敗談や成功談が、ユーザーに信頼感と共感を与えます。体験談の掲載は、Experience(経験)を高めることに寄与するでしょう。特に医療、美容、金融、商品レビューなどの分野では、実際にそのサービスや商品を利用した人の声を掲載することが求められるでしょう。体験談は情報としての被りが少ない傾向にあるため、独自性の高いオリジナルコンテンツとして評価されやすくなります。また、体験談だけでなく、自社で調査したアンケート結果などを掲載することも有効です。
写真・動画などの一次情報の活用
テキストだけでなく、オリジナルで撮影・作成した画像や動画などの一次情報を掲載することも、Experience(経験)を高めることに有効です。レビュー記事ではやはり、実物の写真や操作中の様子、ビフォーアフターの比較などを掲載することで、ユーザーに具体的なイメージを持たせることができ、情報の裏付けとして機能させることができます。SEO的にも、(それが必要であるという前提で)画像や動画が用意されていることが上位表示につながることがあるため、体験が重要なジャンルでは必須の要素といえるでしょう。
使用履歴や思考プロセスの掲載
ユーザーにとって本当に役立つ情報とは、単なる結果や結論だけでなく、結論に至る過程や判断理由が含まれたものといえます。「なぜその商品を選んだのか」「どんな手順で問題を解決したのか」「他に検討した選択肢は?」といったプロセスを語ることで、経験の厚みを感じさせることができ、Experience(経験)性を高めます。読者の意思決定を助けるものになり、Googleに有用性を評価させやすくなります。
専門家による執筆・監修
医療、法律、金融などのYMYL分野では特に、専門資格を持つ人による執筆や監修が、Expertise(専門性)を高めるために非常に重要な手段です(YMYLでないジャンルでも、執筆・監修の表示は有用です)。記事末尾に監修者の名前やプロフィール、所属機関などを記載し、個人や組織のページへの発リンクを促すなどしてその専門性を証明することで、検索エンジンからの評価につながり、ユーザーの信頼も高まります。
専門用語や根拠データの明示
Expertise(専門性)高い内容には、統計データ、研究結果などを根拠として明示することが不可欠です。信頼できる公的機関や学術論文、業界団体のデータなどに基づいて論理的に説明を行うことで、ユーザーにとっても納得感のあるコンテンツになります。引用した論文には、引用元のサイトへの発リンクを渡し、Googleにシグナルを送ることも大切です。また、専門用語を使う際は、その意味を初心者向けに丁寧に補足することで、専門性とユーザビリティの両立が可能になります。
専門的なページの量産
特定ジャンルのExpertise(専門性)を高めるためには、1ページだけ用意するだけでなく、その記事に関連するさらに詳細なトピックを網羅することも有効です。具体的には、1つ専門的な記事を作成したら、その記事のある部分を取り上げてさらに詳細な記事を作成し、内部リンクを渡し合う、といったようにです。それを繰り返して、専門的な情報をクラスター(塊)としてサイト内に作ることで、より強固な専門性をもったコンテンツを提供することができます。
信頼される外部サイトからの被リンク獲得
他の信頼性あるサイト、特に公的機関や大手メディア、大学、業界団体などから自サイトへリンクが張られていることは、Authoritativeness(権威性)を高め、Googleにとって「このサイトは信頼に値する情報源である」と評価する根拠になります。質の高い被リンクは、SEOの順位向上に直結する重要な要素でもあります。リンクを得るためには、独自性があり、有益かつよくまとまったコンテンツを継続的に発信することが基本です。外部との協業や寄稿もリンクを得るために効果的な手段です。
業界内での掲載・引用実績の紹介
自分のコンテンツが他の権威あるメディアや専門家に取り上げられた実績は、サイテーションが高まりAuthoritativeness(権威性)の証拠になります。たとえば「〇〇新聞に掲載されました」「△△協会の公式サイトで引用されています」といった具体的な実績を明示することで、読者の信頼を得やすくなります(オフラインよりもWebサイトの方が効果は高いです)。検索エンジンもこうした第三者からの評価を間接的に評価材料と捉えるため、記事内に引用実績や掲載メディアの情報を記載することは、SEO対策としても効果的です。
whois情報を公開する
ウェブサイトのAuthoritativeness(権威性)を高めるためには、whois情報の公開が有効な手段のひとつです。whoisとは、ドメイン名の登録情報を検索できる仕組みで、サイトの所有者や連絡先、登録事業者などが記録されています。これを公開設定にすることで、第三者が「誰がこのサイトを運営しているのか」を確認でき、透明性を高める効果があります。
whois情報を設定・公開するには、まず利用しているドメイン管理サービスにログインし、該当ドメインの設定画面にアクセスします。多くのサービスでは「whois情報公開設定」といったメニューがあり、ここで情報登録をすることで、自身の登録情報をwhoisで表示させることができます。法人であれば、会社名や所在地を記載しておくことで、より明確な運営者情報となります。
ただし、個人サイトの場合はプライバシー保護の観点から、すべてを公開するのが難しいケースもあります。その場合でも、最低限、サイト内に運営者情報やお問い合わせページを用意し、whois情報と合わせて実在性を示すことが重要です。
運営者情報・問い合わせ先の明示
誰が、どのような立場で情報を発信しているかを明確にすることは、サイトのTrustworthiness(信頼性)を高める基本です。運営会社名、代表者名、所在地、連絡先などを「会社概要」や「お問い合わせ」ページにしっかり記載することで、読者は安心して情報を受け取ることができます。また、責任の所在が明確であることは、Googleの検索品質評価でも重視されるポイントです。匿名性の高いサイトは信頼性が低いと見なされる可能性があるため、情報開示は不可欠といえます。
セキュリティ対策(SSL対応など)の実施
ユーザーの個人情報を取り扱う可能性があるサイトでは、Trustworthiness(信頼性)を担保するためにSSL(https化)による通信の暗号化が必須です。Googleもセキュアな接続を提供しているサイトを優先的に評価する傾向があり、SSL非対応のサイトは検索順位にも悪影響を及ぼす可能性があります。さらに、プライバシーポリシーやクッキーポリシーの設置も、ユーザーの信頼を得る上で欠かせない要素です。サイト全体で「安心して利用できる環境」を整備することが求められます。
情報の正確性と更新履歴の提示
Trustworthiness(信頼性)のあるサイトであるためには、常に正確で最新の情報を提供し続ける姿勢が必要です。そのためには、記事に更新日を明記したり、重要な修正内容を追記することで、ユーザーに「情報がメンテナンスされている」印象を与えられます。特に法律や制度が頻繁に変わるジャンルでは、古い情報を放置すると信用を失う原因となります。定期的な見直しと明確な更新履歴の表示により、継続的に信頼性を保つことができます。
E-E-A-T評価を下げる要因
E-E-A-Tを満たしていない、あるいは欠如していると判断されると、検索順位の低下だけでなく、ユーザー離れを引き起こす可能性が高まります。以下に、E-E-A-Tを損なう3つの典型的な要因を解説したので、参考にしてください。
コンテンツの質の低さ
質の低いコンテンツは、検索エンジンだけでなく読者にとっても大きなストレスになります。代表的な例として、内容の薄い情報の寄せ集め、他サイトの内容を要約しただけの記事などが挙げられます。また、文章の構成が悪く見出しが適切でない、結論が曖昧、読者の疑問に答えていない場合も、検索順位の評価を落とす原因となります。コンテンツは「ユーザーの課題をどう解決できるか」を軸に設計する必要があり、それが欠けるとE-E-A-Tのすべての要素が弱くなり、SEO効果を低下させることにつながるでしょう。
信頼性の欠如
特にYMYL領域においては、執筆者の氏名や経歴が明示されていない、出典や根拠が記載されていない、誤情報に対して訂正や更新が行われていないといった場合、サイトは「信頼できない情報源」と見なされ、検索順位を落としてしまいます。また、SSL未対応で通信が暗号化されていない、問い合わせ先が不明、プライバシーポリシーが存在しないといった技術的な問題も、ユーザーに不信感を与える要因です。信頼されるサイトになるには、誰が・なぜ・どのように情報を発信しているのかを常に明確に示し、誤りに対しても誠実に対応する姿勢が求められます。
更新の停滞
いかに優れたコンテンツであっても、時代遅れの情報のまま放置されていれば、E-E-A-Tの「信頼性」や「専門性」は次第に損なわれていきます。たとえば、制度改正後も古い法律やルールを現行のものとして記載している記事、すでに終了したキャンペーン情報を過去にあったものとして明示していないページは、ユーザーの誤解を招く恐れがあります。Googleも「最新かつ正確な情報提供」を重視しており、記事の更新頻度やリライト履歴はSEOに関わるとされています。更新日を記載していない場合や、修正箇所を明確にしていない場合も、検索エンジンとユーザー双方から「情報鮮度が低い」と判断される可能性があり、情報のアップデートがなされていないことは、「運営の手が止まっている」と見なされ、サイト全体の評価にも波及します。定期的な見直しと更新作業は、E-E-A-Tを維持・向上させるための基本的な対策といえるでしょう。
まとめ:ユーザー第一の姿勢こそがE-E-A-T対策の本質
E-E-A-Tを高める施策には、体験談の活用や専門家の関与、サイト構造の整備など、さまざまな対策があります。しかし、最も大切なのは「ユーザーにとって本当に価値のある情報とは何か」を常に考え抜く姿勢です。SEOにおけるE-E-A-T対策は、テクニックの積み重ねというよりは、ユーザーの信頼を得るための誠実な情報提供の延長線上にあるものです。その上で、Googleの評価基準や検索エンジンに伝わりやすい構造を意識した、正しいSEOの作法を加えることで、より多くの人に価値ある情報を届けることができます。小手先ではない、本質を捉えたE-E-A-T対策を心がけましょう。